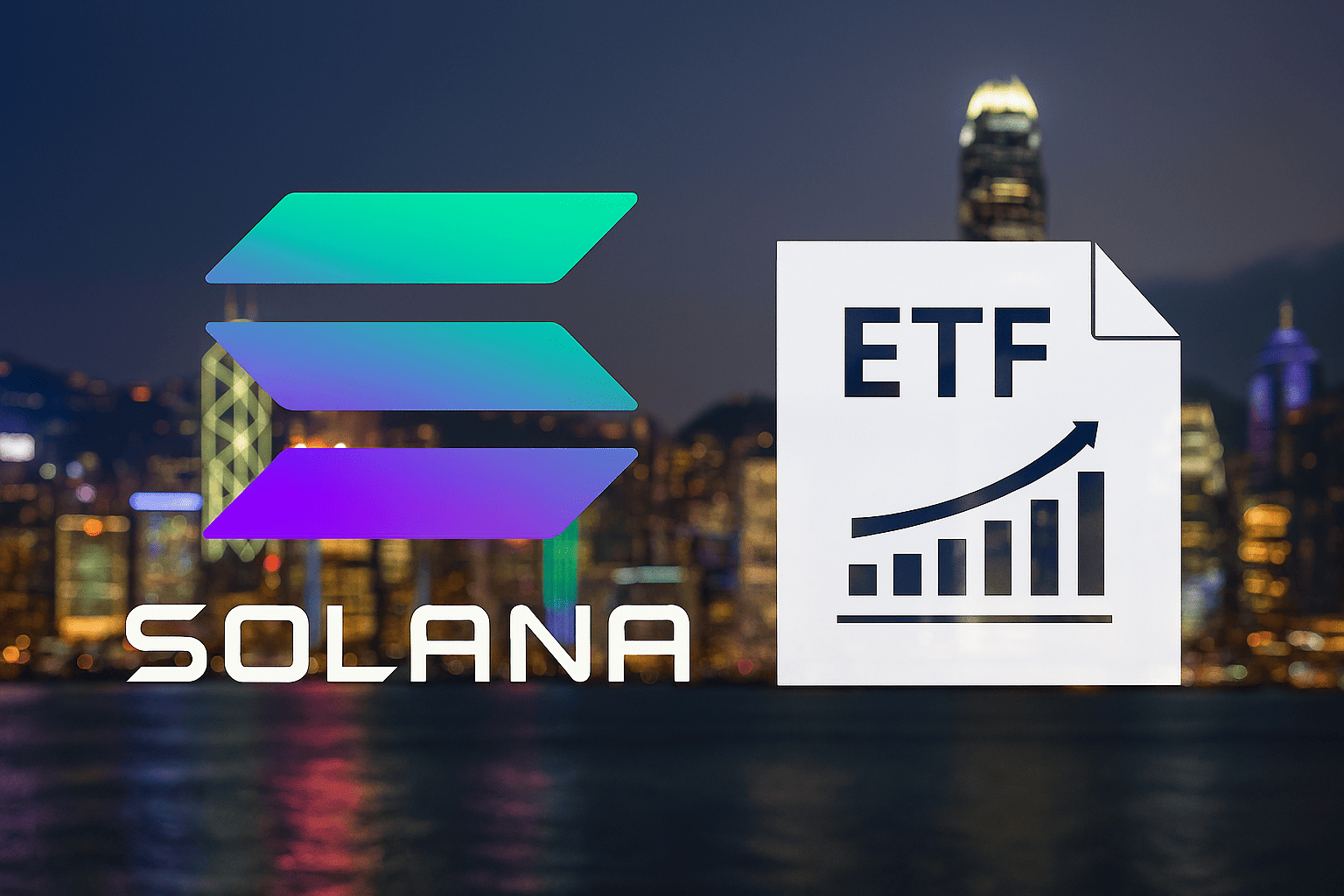ソラナETF承認とエコシステム拡張 | 香港発の現物上場と次世代端末
2025年10月22日、香港証券監督委員会(SFC)は、アジア初となるソラナ(SOL)現物ETFを正式に承認した。運用はChinaAMC(香港)が担い、ETFは「華夏ソラナETF」として10月27日より香港証券取引所で取引開始となる。これは、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)に続く3番目の仮想通貨現物ETFであり、米国市場に先駆けた上場となる。
この承認は、香港が仮想資産の制度整備を積極的に進める姿勢の表れであり、2023年の仮想資産サービスプロバイダー(VASP)制度導入以降、現物ETFの承認が加速している。ソラナはDeFi、NFT、ゲーム領域での高速処理能力を評価されており、機関投資家の分散投資先として注目されていた。
ETF承認のタイミングで、ソラナ・モバイルは仮想通貨スマホ「Saga」のサポート終了を発表。Sagaは2023年に発売され、ミームコインのエアドロップ戦略で話題を集めたが、2万台完売を達成した後、次世代端末「Seeker」への移行が始まった。Seekerは既に15万台以上の予約を獲得しており、Web3対応端末としての普及が期待されている。
市場では、SOL価格が日足チャートでダブルボトムを形成しており、250ドルへの回復が視野に入っているとの分析も出ている。ETF承認による資金流入期待、端末刷新によるエコシステム拡張、価格反発のテクニカル要因が重なり、ソラナは制度・技術・市場の三方向から評価を高めている。
さらに、香港証券取引所が仮想通貨保有企業の上場に慎重姿勢を示す中で、ソラナETFの承認は例外的な制度先行を意味し、アジア太平洋地域における仮想資産政策の分岐点とも言える。米国ではSOLの現物ETFは未承認であり、香港が先行することで、グローバルなETF競争においてアジアの存在感が高まる可能性がある。
この動きは、ソラナが単なる高速チェーンではなく、制度的に認知された投資対象へと進化したことを示す。今後、SOLを組み込んだポートフォリオ設計や、スマートフォンを通じたユーザー獲得戦略が加速する見通しだ。
ビットコイン市場の揺らぎ | クジラの動向とETF資金移動
ビットコイン(BTC)は11万ドルを突破したものの、複数の大口投資家(クジラ)がショートポジションを構築し、価格の天井形成を警戒する動きが広がっている。著名トレーダーのピーター・ブラント氏は、BTCのチャートが1970年代の大豆市場に酷似していると指摘し、供給過剰による急落リスクを示唆した。
一方、ブラックロックが主導するETFへの資産移動も進行中で、初期のBTC保有者が自己保管からETFへと資産を移している。これは流動性向上と機関投資家の受け皿形成を目的とした動きとされる。
さらに、スペースXが2億5700万ドル相当のBTCを移動したことが報じられ、財務戦略や売却の可能 A性を巡る憶測も浮上している。ETFフローは資金ローテーションを示唆しており、BTCはゴールドや株式と異なる独自の値動きを見せている。
ステーブルコインの拡張と金融包摂 | USDTユーザー5億人突破
テザー(USDT)は2025年10月22日、ユーザー数が5億人に到達したと発表。時価総額は1,820億ドルに達し、ステーブルコイン市場の約70%を占める規模となった。CEOのパオロ・アルドイノ氏は「史上最大の金融包摂」と評価し、銀行口座を持たない層へのアクセス手段としての役割を強調した。
米国では2025年上半期の仮想通貨取引高が前年比50%増の1兆ドルを超え、ステーブルコイン取引は83%増と過去最高を記録。トランプ政権下での規制緩和や市場拡大が背景にある。
また、BTCのL2ソリューション「Arkade」がベータ版を公開し、オフチェーンでステーブルコインやレンディング機能を提供する基盤として注目されている。ライトニングネットワークを補完する新たなインフラとして、BTC上でのステーブルコイン活用が現実味を帯びてきた。
イーサリアムの技術進化と財団批判 | フサカ導入と内部構造の揺らぎ
イーサリアムは次期アップグレード「フサカ」でEIP-7825を導入し、1取引あたりのガス上限を約1,678万に制限する方針を発表。ホレスキーとセポリアで既に稼働しており、12月3日のメインネット実装が予定されている。
一方、元コア開発者シラージ氏が財団の体制を批判し、ヴィタリック・ブテリン氏を中心とした支配層の存在や報酬格差を指摘。ポリゴンCEOも不満を表明しており、内部構造の透明性が問われている。
シャープリンク・ゲーミングは7650万ドルの資金調達を受け、ETH保有量を85万9853ETH(約35億ドル)に拡大。企業によるETH蓄積が進む中、技術進化と統治構造の両面でイーサリアムの将来像が揺れている。
規制と制度改正 | 銀行の仮想通貨投資とインサイダー規制強化へ
金融庁は、銀行および保険会社がビットコインなどの仮想通貨を投資目的で保有できるよう制度改正の検討を正式に開始。金商法の適用を前提に、売買や保管に関するルール整備が進められている。
同日、金融審議会では暗号資産のインサイダー取引規制案が提示され、DEXやP2P取引も対象に含まれる方針が示された。銀行本体の取扱いは慎重に進める一方、子会社には門戸を開く方向で議論が進んでいる。
また、香港証券取引所は仮想通貨保有企業5社以上の上場計画に異議を唱え、インドや豪州も同様の反対姿勢を示している。アジア太平洋地域では規制強化の流れが顕著で、日本の制度設計が注目されている。
ETFと機関投資家の動向 | 日本企業の組み入れとギャラクシーの増益
2025年10月22日、米ビットワイズが提供する「Bitwise Bitcoin Holdings ETF(OWNB)」に、日本企業リミックスポイントが新規採用された。同社は1,382BTC(約227億円)を保有しており、組み入れ比率は2.03%。メタプラネット(2.70%)やネクソン(1.65%)と並び、日本企業の存在感が高まっている。
このETFは、1,000BTC以上を保有する企業を対象に、株式投資を通じてビットコイン保有企業へのエクスポージャーを提供する設計。現在、70社以上が合計65万BTC以上を保有しており、機関投資家が間接的にBTCにアクセスする手段として注目されている。
同日、仮想通貨金融企業ギャラクシー・デジタルは第3四半期決算を発表し、取引活動の活発化と資産運用事業の拡大により大幅な増益を記録。機関投資家の需要が依然として高く、ETFやカストディサービスを通じた資産運用が拡大している。
これらの動きは、仮想通貨が「企業の財務戦略」や「資産運用の対象」として定着しつつあることを示しており、ETF市場の成熟とともに、企業のBTC保有が投資家の評価軸に組み込まれ始めている。
小売と予測市場の拡張 | Beallsの仮想通貨決済導入とポリマーケットの新機能
2025年10月22日、米国の老舗百貨店チェーン「Bealls Inc.」が、仮想通貨決済の導入を正式発表した。創業110年を迎える同社は、デジタル決済プラットフォーム「Flexa」と提携し、全米22州に展開する660店舗で、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、USDCなど99種類以上の仮想通貨による支払いを受け付ける。対応ウォレットは300種類以上にのぼり、サブセカンド(1秒未満)の決済速度や自動通貨対応機能を備え、既存のレジシステムとシームレスに統合されている。
Beallsのマット・ビールCEOは「仮想通貨は世界の取引方法を変えるだろう。Flexaとの提携は、今後110年にわたるイノベーションの継続を意味する」と述べており、同社の戦略は伝統的な小売業と新興金融技術の融合を目指すものと位置づけられている。
同日、分散型予測市場プラットフォーム「ポリマーケット」は、チェーンリンク(Chainlink)のオラクルネットワークと連携し、15分間で完結する仮想通貨価格予測市場を開始した。ユーザーはBTCやETHの価格が15分後に上昇するか下落するかを予測し、Yes/No形式のシェアを購入する仕組み。決済にはUSDCやUSDTが使用され、非保管型設計により資産管理権を保持したまま参加できる。
この新市場は、従来の金融市場における分単位のオプション取引に似ているが、証券口座やレバレッジを必要とせず、より簡素な参加設計が特徴。リアルタイムの価格データはチェーンリンクのオラクルが提供し、結果判定の信頼性を担保している。
Beallsの仮想通貨決済導入とポリマーケットの短期予測市場は、消費者と投資家の両面で仮想通貨の実用性と即時性を押し広げる動きとして注目される。